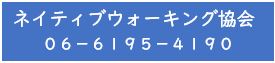改善効果を上げるために重要で、忘れがちな視点
今回は治療家の方が、すぐに忘れてしまう
とても重要な視点の話をします。
ちょっとした問題ですが、
特に慢性症状において
改善にはどちらの方が有効な手段だと思いますか?
①適切な治療を受ける(良いことを増やす)
②体に負担になっている生活習慣を改善する(悪いことを減らす)
これは基本的に、
②の方が改善効果が高いはずです。
特に慢性症状においては
圧倒的にそうです。
それはなぜか
一番大きなポイントは、
人間には自然治癒力が存在しており
基本的には、放っておいても回復するからです。
では回復をしない(慢性化する)とすれば、
どんなケースが考えられるでしょうか。
それは日常で回復力以上に、
負担をかける動作や姿勢などの
「悪習慣」が続いている場合、
というのがほとんどではないでしょうか。
一見当たり前の、よく知られた話を
したりしているように聞こえるかもしれません。
しかしここに、あなたの治療院が
確かな改善で、評判の高い治療院になれるかどうかの
大きなポイントが隠されているのです。
あなたが何らか治療を施しているのに、
その方がなかなか改善していかないとすれば、
まず疑うべきはその方の日常なのです。
なぜなら、乱暴な話をすればあなたが
「適切」な治療ができていなかったとしても
マイナスさえ作っていなければ、
自然治癒力により改善するはずなのですから。
という事はあなたは、その患者さんが
日常の「どんな動作」「どんな姿勢」が
負担になっているのかを、知らなくてはいけません。
そしてそれらを改善指導できるようになるべきでしょう。
そうすれば、はっきりってしまえば
適切な治療施すよりも、大きな改善効果があります。
私はなかなか改善していかない長患い患者さんに、
「何が原因で、どうすればきちんと改善していくのか」
を追求していった結果、結局は「生活習慣の改善」
というところに辿り着きました。
なので「姿勢」や「歩き方」はもちろん、
「肩の動かし方」から「お腹の力の入れ方」まで
様々な動作や姿勢の改善を指導します。
そしてその結晶のようなものが、歩行指導です。
外反母趾はもちろんですが、
膝の痛みや股関節の痛み等にも
歩き方は大きく影響しています。
歩き方が変わらなければ、
いつまでも痛みが引かないというケースが
よくあります。
そして足の改善は、体全体を支えているのは
足であると言うことから、
全身の姿勢にも影響します。
その結果、腰や首肩の疾患も
大きく改善するケースが後をたちません。
あなたがもし、治療の現場に携わる方だとすれば
「足の仕組み」や「足の病理」「足のメカニズム」に
精通しておく事は、必ず大きな力になります。
ぜひ詳しく学んでみてください。
その改善効果の大きさに、
そしてその改善の影響の範囲の広さに
驚かれることだと思います。