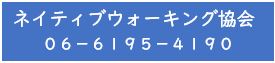始めた当初はそれで充分採算のとれるモデルだとしても、
時代の流れや移り変わり、地域環境の変化などにより、
いくら努力してもそもそも回らない
ビジネスモデルになっていることは、しばしばあります。
例えば、一時社会問題になった牛丼店などの
「ワンオペ」などがそれにあたります。
1人で店を回すということは、トイレにすらいけない、
もちろん緊急時にどうにもできないということ。
当初は利益があり2人以上でも利益は出ていたのでしょう。
1人でなければ利益が出ないということはそもそももう、
そのビジネスモデル自体に無理があるということです。
この場合どこかの経費だけを下げるなどの対処療法ではなく、
ビジネスモデル全体を見直す必要があります。
治療業界でもこれと似たような問題は、全体的にも部分的にも見受けられます。
例えば一昔前の病気は赤痢やコレラなどの「疫病」が主でした。
このような場合には原因であるウイルスや細菌に対する
抗生物質などの治療が有効でしょう。
しかし現代はそうではなく「生活習慣病」が大半を占めます。
であれば、根本的な改善には当然、生活習慣の改善が必要のはず。
しかし日本の医療はその変化に対応できず、
生活習慣の改善治療はいまだに力を入れられていません。
これは明らかにビジネスモデルに無理があるということ。
なので国民医療費は毎年、どんどん膨れ上がっていくという結果を招いています。
私たちの療術業界の世界でいうと、
メンテナンスという概念もそれに近いものがあると感じています。
治療家は経営の安定のためにも患者さんのためにも、
定期的なメンテナンスを勧める方が多いです。
その是非はともかく、もし治ってしまったとしたら人間は、
心理的に治療院にお金や時間を使うのを、
もったいないと思いがちなもの。
元々そのメンテナンス意識のある方は良いですが、
そうでない方にはそれを覆すための相当な教育や、
意識改革が必要です。
ということは「メンテナンスが必要ですよ」というだけでは、
言う側のただの自己満足で終わります。
もしもそれを事業の一部として成り立たせるなら、
そんな意識改革の教育に時間を割くか、治った人に対する
「治療院ではない次のステージ」を用意するなど、
ビジネスモデルの構築から行なう必要があります。
このようにビジネス全体でなくとも、
うまく回っていない事業や取り組みは、
そもそもいくら努力をしてもうまく回らないという
状態に陥っている可能性も。
見極めは難しいですが、
常に「これでいいのか」という問題を持っていれば、
そんな問題に気付き抜本的な対策に踏み出せる様になってきます。